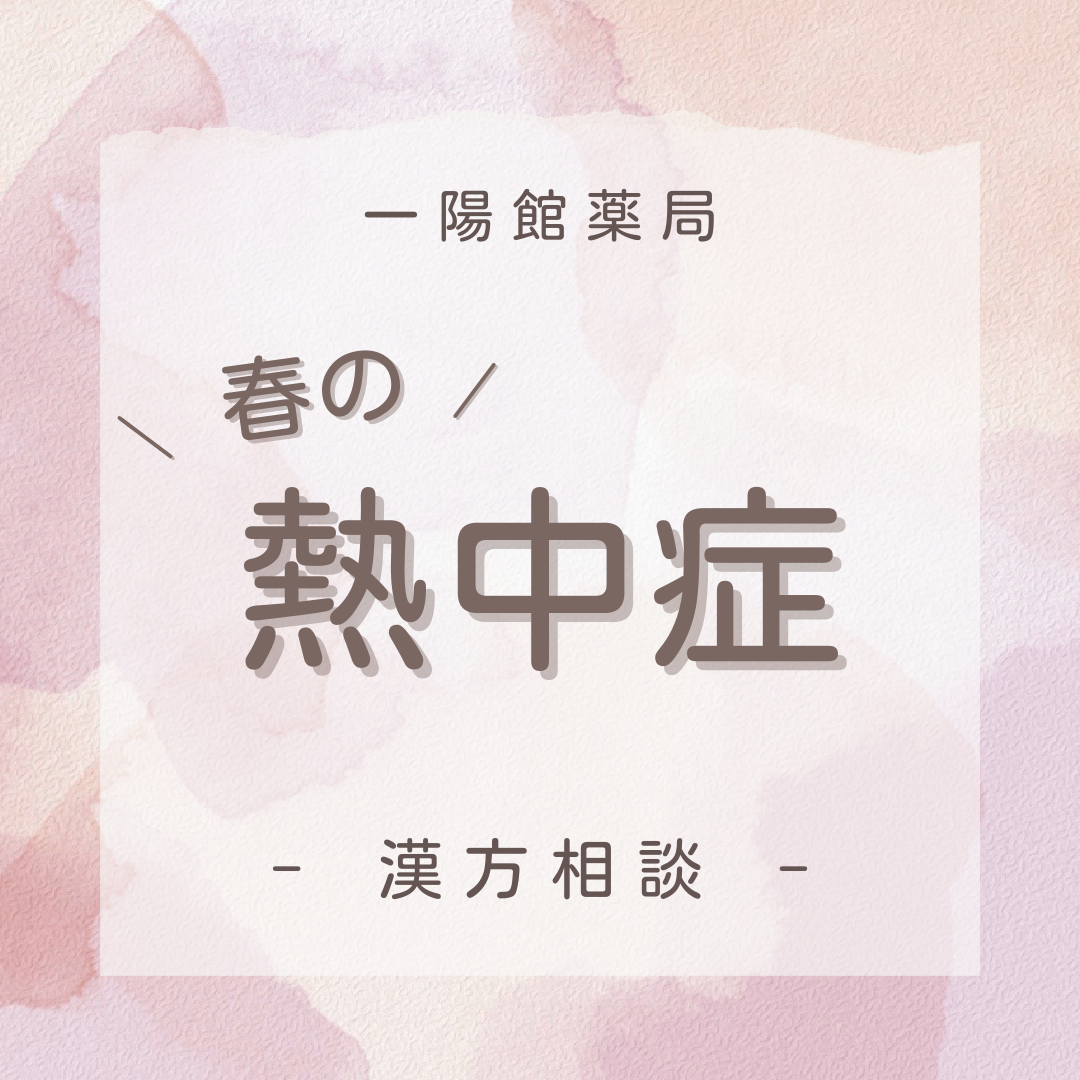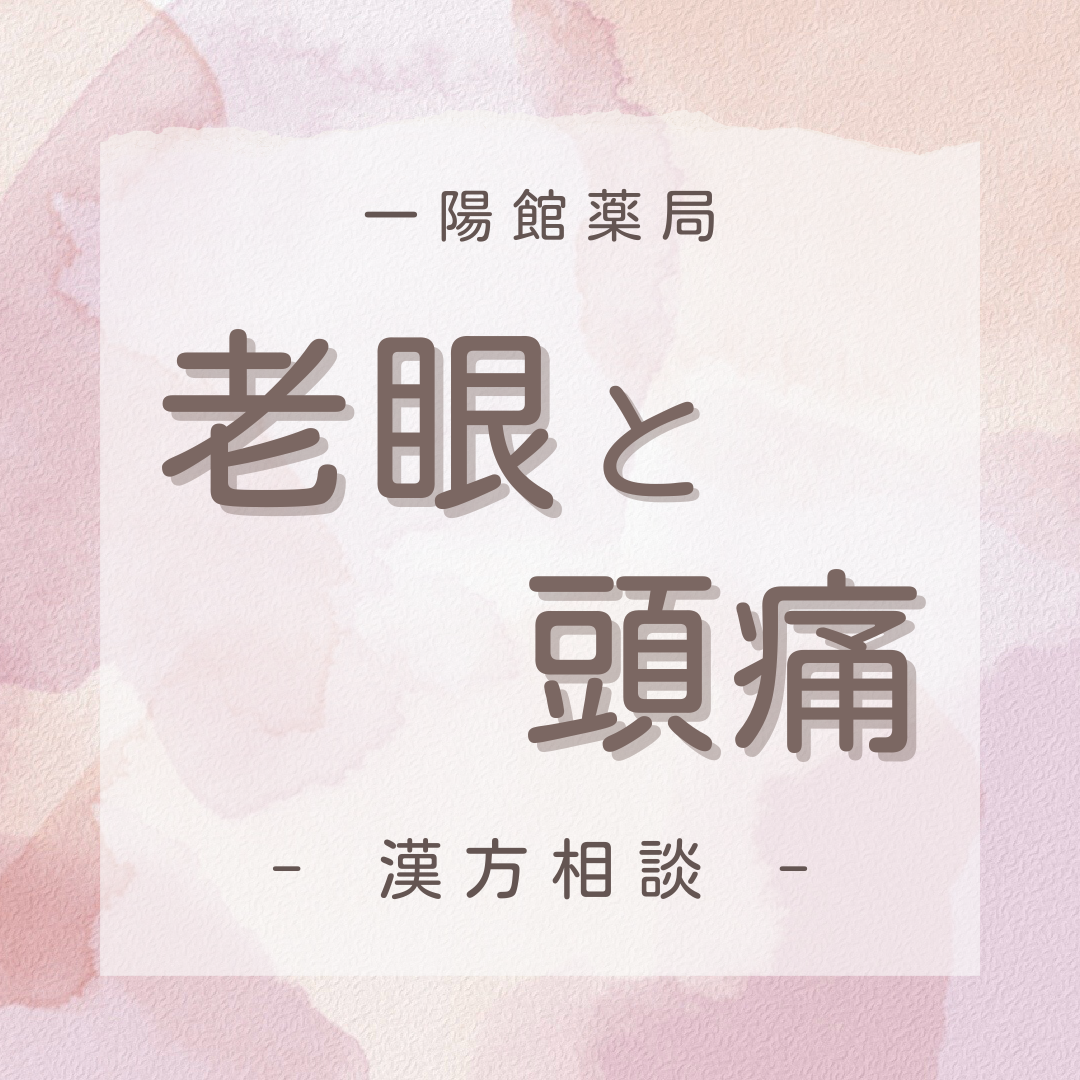止まらぬ咳──”百日咳”
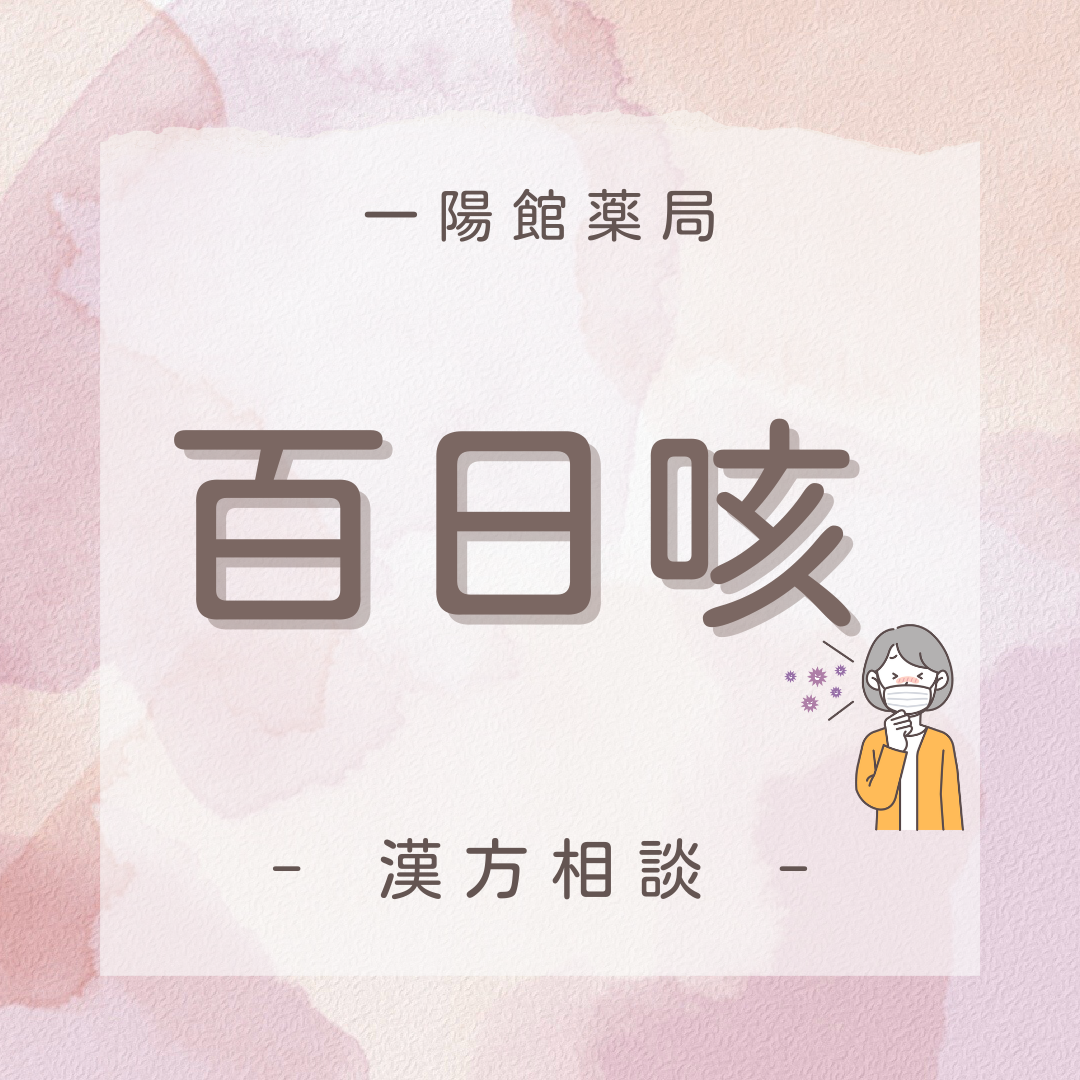
「咳が長引くなあ」と思っていたら、実は百日咳だった──そんな声を最近よく聞くようになりました。特に大人になってからの百日咳は、自覚しにくく、周囲にうつしてしまうことも。
百日咳とは?
百日咳は「Bordetella pertussis(ボルデテラ・パートゥシス)」という細菌によって引き起こされる急性呼吸器感染症です。名前の通り、100日以上も咳が続くことから「百日咳」と呼ばれています。
日本では、かつては乳幼児の病気とされていましたが、予防接種の普及により子どもの重症例は減少。しかしその反面、10代~40代の大人の感染例が増加傾向にあります。2023年の国内データでは、年間約7,000件近い報告があり、そのうちの約60%が成人という報告もあるほどです。
・カタル期(1〜2週間)
風邪のような軽い症状が中心。鼻水、軽い咳、微熱など。
・痙咳期(2〜6週間)
特徴的な連続性のけいれん性咳が出現。咳のあとに「ヒュー」と息を吸う音(笛声)を伴うことも。夜間や運動後に悪化する傾向があります。
・回復期(3週間以上)
咳は少しずつ軽減するが、刺激により再び激しくなることもあるため注意が必要です。
とくに成人は典型的な「ヒュー」という音を伴わない咳が多く、診断が遅れるケースも少なくありません。
東洋医学では、「咳」は単なる症状ではなく、「肺の失調(はいのしっちょう)」や「邪気の侵入」によって引き起こされると考えます。百日咳においては、特に以下のような状態が重なっていると診ます:
風熱犯肺(ふうねつはんはい):
外からの熱邪(風熱)が肺に侵入し、乾いた咳や黄色い痰を引き起こすタイプ。初期に多く見られます。
肺陰虚(はいいんきょ):
咳が長引くことで、肺の潤いが失われ、空咳や痰の少なさ、喉の渇きが目立つタイプ。後期に移行しやすい状態です。
脾虚湿盛(ひきょしつじょう):
長引く体調不良や消化器の不調から痰湿が生じ、痰が絡んだしつこい咳に。回復期に見られることがあります。
漢方では「未病」の考え方が基本です。咳が始まったばかり、あるいは長引いている時には、次のような生活習慣も見直してみましょう。
✔ 温かい白湯をこまめに(肺を潤し、気を通す)
✔ 辛いものや揚げ物を控える(肺の熱を助長しないように)
✔ 夜更かし・喉の酷使を避ける
✔ マスクや加湿器で乾燥対策を
特に春先は、乾燥と気温差で肺がダメージを受けやすいため、予防的ケアとして麦門冬などを配合したお茶や漢方薬を取り入れるのもおすすめです。
百日咳は、ただの咳と思って放置すると、自分だけでなく大切な家族や周囲の人にもうつしてしまう可能性があります。西洋医学での早期の診断・治療も重要ですが、東洋医学の視点からみることで、体のバランスを整え、根本的な体質改善へとつなげることも可能です。
長引く咳に悩んでいる方は、ぜひご相談ください。
営業時間 10:00~18:00
定休日 木・日・祝
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-