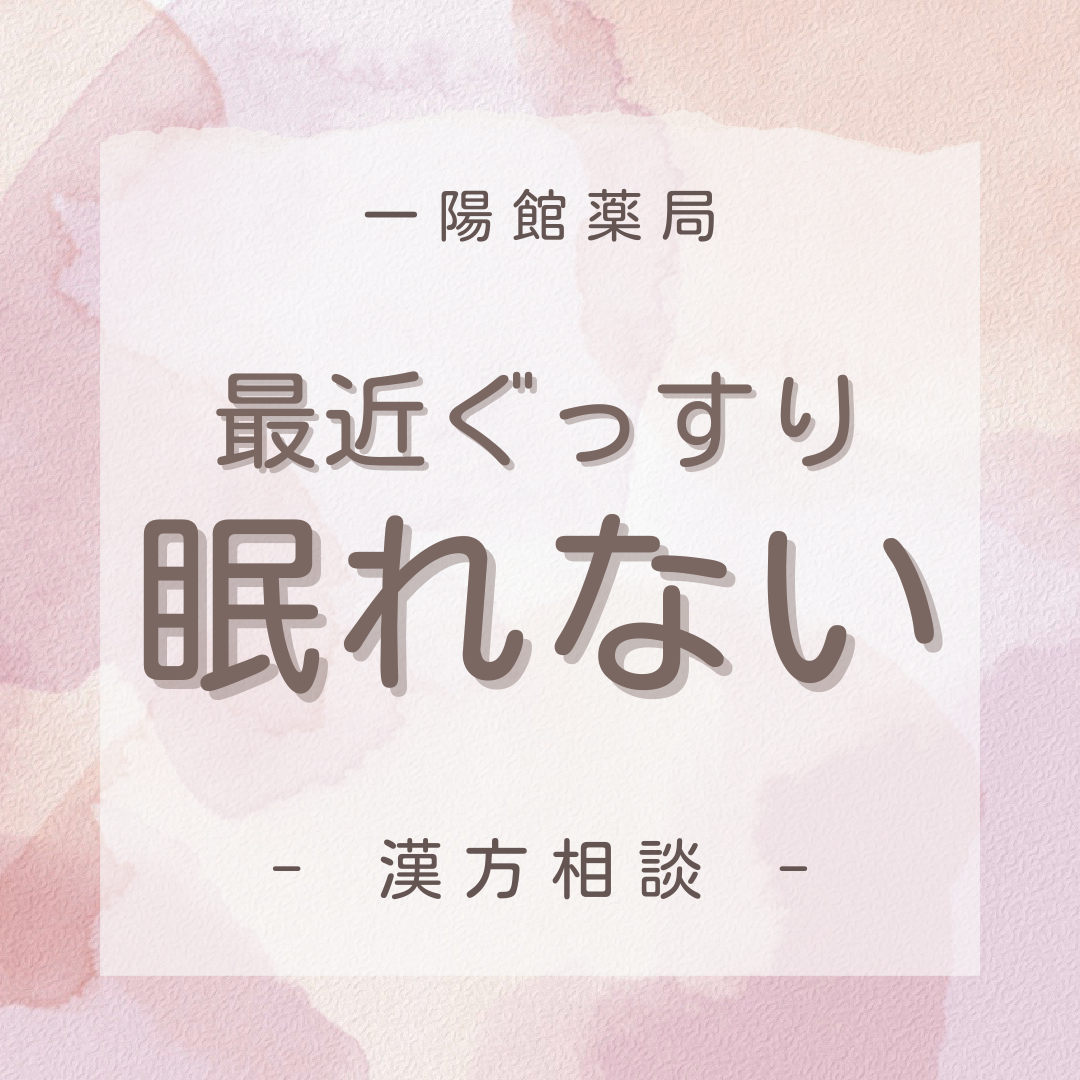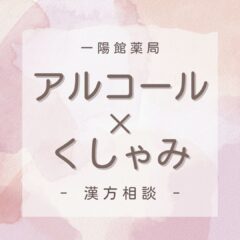春に流行る“リンゴ病”とは?大人も油断できないその症状
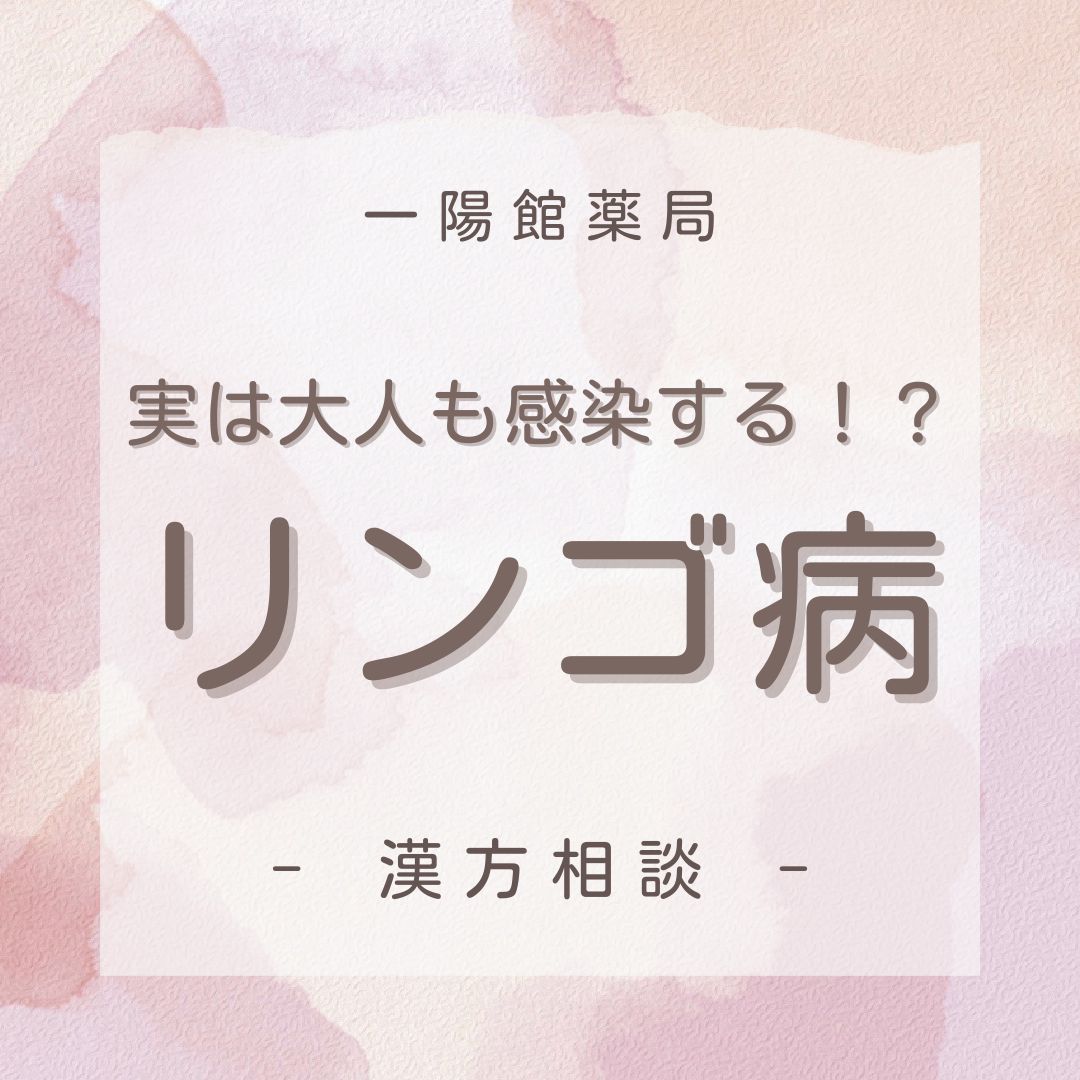
先日「子供がリンゴ病にかかってしまいました。大人もうつりますか?」とご相談をいただきました。子供の頃に発症するイメージが強いリンゴ病ですが、実は大人も感染する厄介なウイルスなのです。
春から初夏にかけて、子どもの頬がりんごのように真っ赤に…そんなとき、耳にするのが「リンゴ病」。
正式には「伝染性紅斑(でんせんせいこうはん)」と呼ばれる感染症です。毎年4月から7月にかけて流行のピークを迎えるこの病気、実は大人にもうつることがあり、油断できません。
リンゴ病の原因は「ヒトパルボウイルスB19」というウイルス。潜伏期間はおよそ4~14日。感染すると最初の数日間は風邪のような症状が現れ、その後、両頬が真っ赤に染まるのが特徴です。
日本では、過去10年間でおおむね5年に1回、大規模な流行が見られ、たとえば2015年には全国で約12万人以上の報告がありました。感染者の約7割は10歳未満の子どもですが、大人に感染した場合、特に女性では関節痛を伴うケースが多く、妊娠中の方は注意が必要です。
漢方では、病気を単なるウイルスや菌の仕業と捉えるのではなく、「正気(せいき)」と「邪気(じゃき)」のバランスの乱れとして考えます。リンゴ病のように、発熱、発疹、倦怠感がみられる疾患は、東洋医学的に「温病(うんびょう)」や「風邪(ふうじゃ)」による体表への侵入と考えられます。
特に春から初夏は「風(ふう)」の邪が強まりやすい季節。風は動きを伴い、皮膚や粘膜など、体表面から入りやすいとされています。リンゴ病で見られる頬の紅潮や、腕・脚に広がるレース状の発疹は、「風熱(ふうねつ)」や「湿熱(しつねつ)」が肌に浮き出ている状態とも捉えられます。
発症してしまった場合、現代医学では対症療法が基本です。薬でウイルスを直接倒すことは難しいため、発熱やかゆみがあれば解熱剤や抗ヒスタミン薬などを使用しながら、自宅での安静が勧められます。
一方、漢方では、発熱や発疹の状態
たとえば、
・熱感が強く、喉が渇くタイプ
・発疹がかゆくて赤みが強い場合
・関節痛やだるさが一番つらい
などの症状では、適している漢方薬が異なるのです。
そのため自己判断での使用は避け、専門家の診断を受けることが大切です。
リンゴ病の流行を防ぐワクチンはまだ存在していません。そのため、基本は「予防」が第一。
手洗い・うがいといった日常の衛生習慣はもちろんですが、漢方の知恵としては「衛気(えき)」と呼ばれる体表を守るエネルギーを強く保つことも大切です。
衛気は、現代風に言えば「免疫力」に近い存在。これを養うには、
・睡眠をしっかりとる
・冷たいものを控えて胃腸を冷やさない
・食事は旬のもの、消化の良いものを選ぶ
など、シンプルながらも確実なケアが大切です。
おすすめの食材は「豆類」「青菜」「黒きくらげ」「はとむぎ」など。
これらは身体の余分な熱や湿を排出しながら、内側から健やかな肌を保つサポートをしてくれます。
リンゴ病は比較的軽症で済むことが多いとはいえ、大人がかかると辛い症状が長引くこともありますので、特にお子さんやご家族が感染した場合は、早めの対応と体のケアを忘れずに。東洋医学の知恵も上手に取り入れながら、日々の体調管理に役立てていただければと思います。
営業時間 10:00~18:00
定休日 木・日・祝
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-