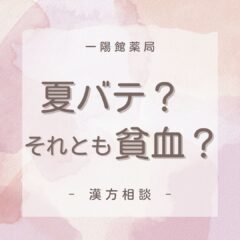日本人の体に合った、昔ながらの食養生
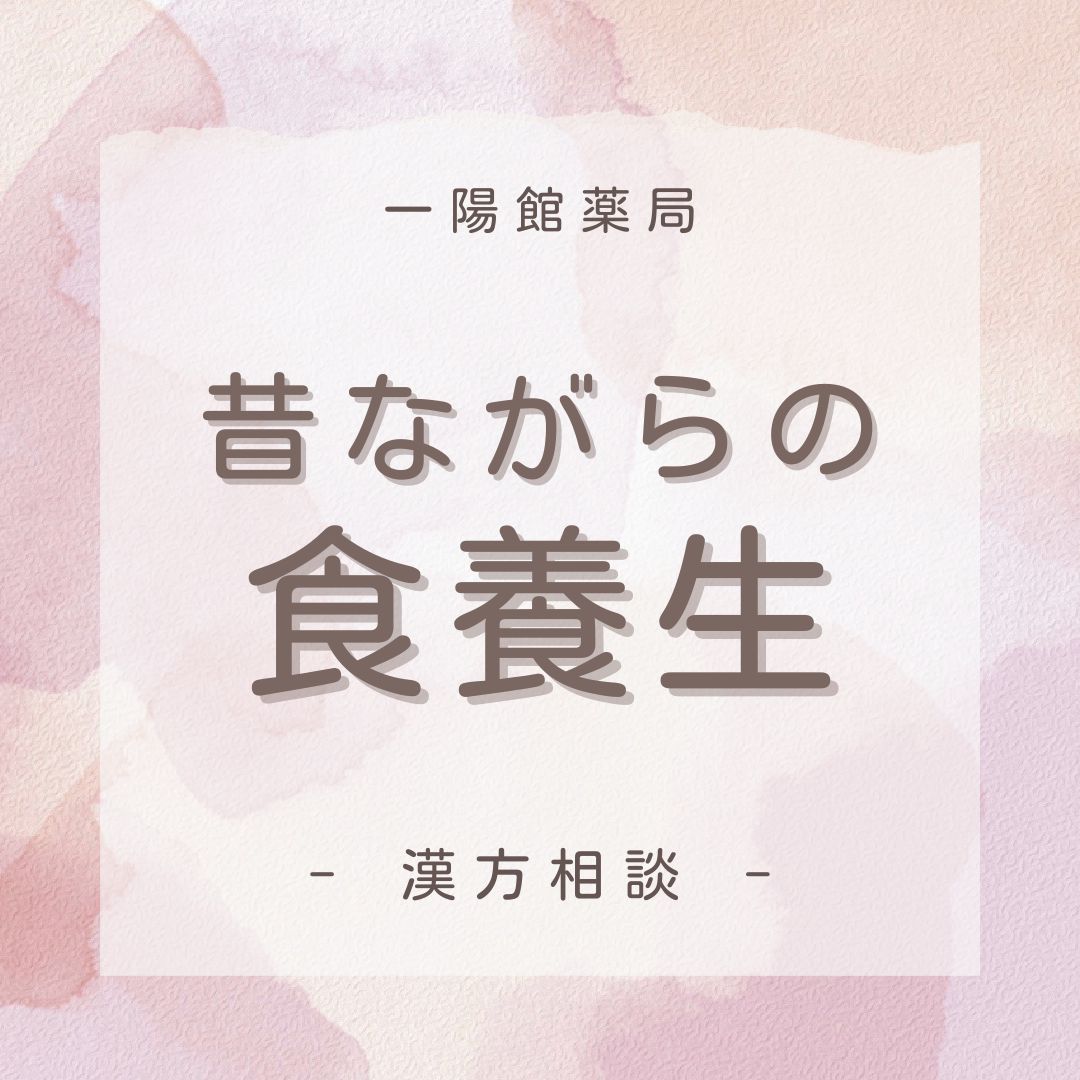
漢方相談にいらっしゃるお客様から、
「日ごろの食事でどのような点に気を付けたらよいか」とご質問いただくことがあります。
現代の食卓には、カタカナの食べ物があふれています。
スムージー、スープ、パスタ、パンケーキ、ドレッシング…。
どれも便利で、おしゃれで、美味しいですよね。
私たちの毎日の食卓には、たくさんの選択肢があります。
「お味噌汁」は書けるけど、「スープ」は書けますか?
ふと気づくと、漢字で書けない食べ物ばかり食べていませんか?
ちょっと立ち止まって、「漢字で書ける食べ物」ってどれだけあるだろう?と考えてみると、そこには、体をやさしく整えてくれるヒントが詰まっているように感じます。
「食は命を養うもの」とされ、私たちの“気・血・水”のめぐりを整えるためにも、毎日の食事が最も大切と考えます。
そして、体を冷やさず、消化しやすく、自然のエネルギーをたっぷり含んだ食材は、やはり“漢字で表せるようなもの”に多く、日本や中国など東洋の文化で長く親しまれてきたものが、季節や体のバランスを整える力があると、漢方の世界では考えられています。
たとえば、「大根」「小松菜」「葛」「豆腐」「生姜」など。
どれも自然の恵みを感じさせる、体を養う優しい食べ物です。
一方、「ハンバーグ」「ドレッシング」「スムージー」「グラノーラ」など、カタカナで表記される食べ物の多くは、欧米由来であり、加工度が高く、砂糖や油脂が多い傾向にあります。
カタカナ食が続くと、こんな体の不調が…
🔸 脾(ひ)=消化器の弱り
漢方では、胃腸の働きを「脾(ひ)」と呼びます。冷たいジュースや生クリームたっぷりのケーキばかり食べていると、この「脾」が弱り、疲れやすく、むくみやすくなります。
🔸 湿(しつ)が体にたまる
カタカナ食は体に余分な「湿(しつ)」を生みやすく、重だるさや頭痛、めまいなどの原因となることも。これは“体の中がじめじめしている”ような状態で、東洋医学では梅雨どきの不調とも深く関係しています。
🔸 血の巡りの停滞(瘀血)
甘いお菓子や脂っこいカタカナ食は、血流を滞らせ、「瘀血(おけつ)」と呼ばれる状態を招くこともあります。肩こり、冷え、婦人科トラブルなど、さまざまな不調につながるのです。
だからこそ、漢字で書ける食べ物を選びたい
・お味噌汁(発酵食品・温かい・胃腸を助ける)
・和菓子(小豆・寒天・白砂糖控えめ)
・根菜の煮物(大根・人参・ごぼうなど、温性で体を巡らせる)
・葛湯(くずゆ)(お腹にやさしく、寒さを取り除く)
・雑穀ごはん(気を補い、腸を整える)
これらはどれも、「気血水」の巡りを良くし、「五臓六腑」を健やかに保つ力があるとされています。漢字で書ける=昔から人々の生活の中で受け継がれてきた「養生の知恵」でもあるのです。
もちろん、絶対に避けなければいけないわけではありません。
でも、「ちょっと不調が続く」「疲れやすい」そんなときは、“漢字のごはん”に立ち返ることが、何よりの養生になります。
漢字で書ける食材には、「体が喜ぶ食べ物」のヒントが詰まっています。
見た目が華やかで一時的に満たされるカタカナ食も良いですが、毎日続ける食事こそ、未来の自分の体をつくるもの。
心がざわざわした日も、体が疲れている日も。
何を食べようか迷ったときは、まずは1日1品、「漢字で書けるごはん」に変えてみませんか?
あなたの体は、きっとすぐにその違いに気づいてくれるはずです。
ご相談をご希望の場合は、電話またはLINEからご予約ください。
営業時間 10:00~18:00
定休日 木・日・祝
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-