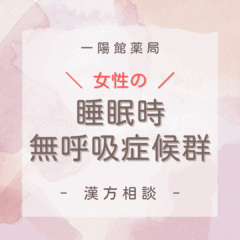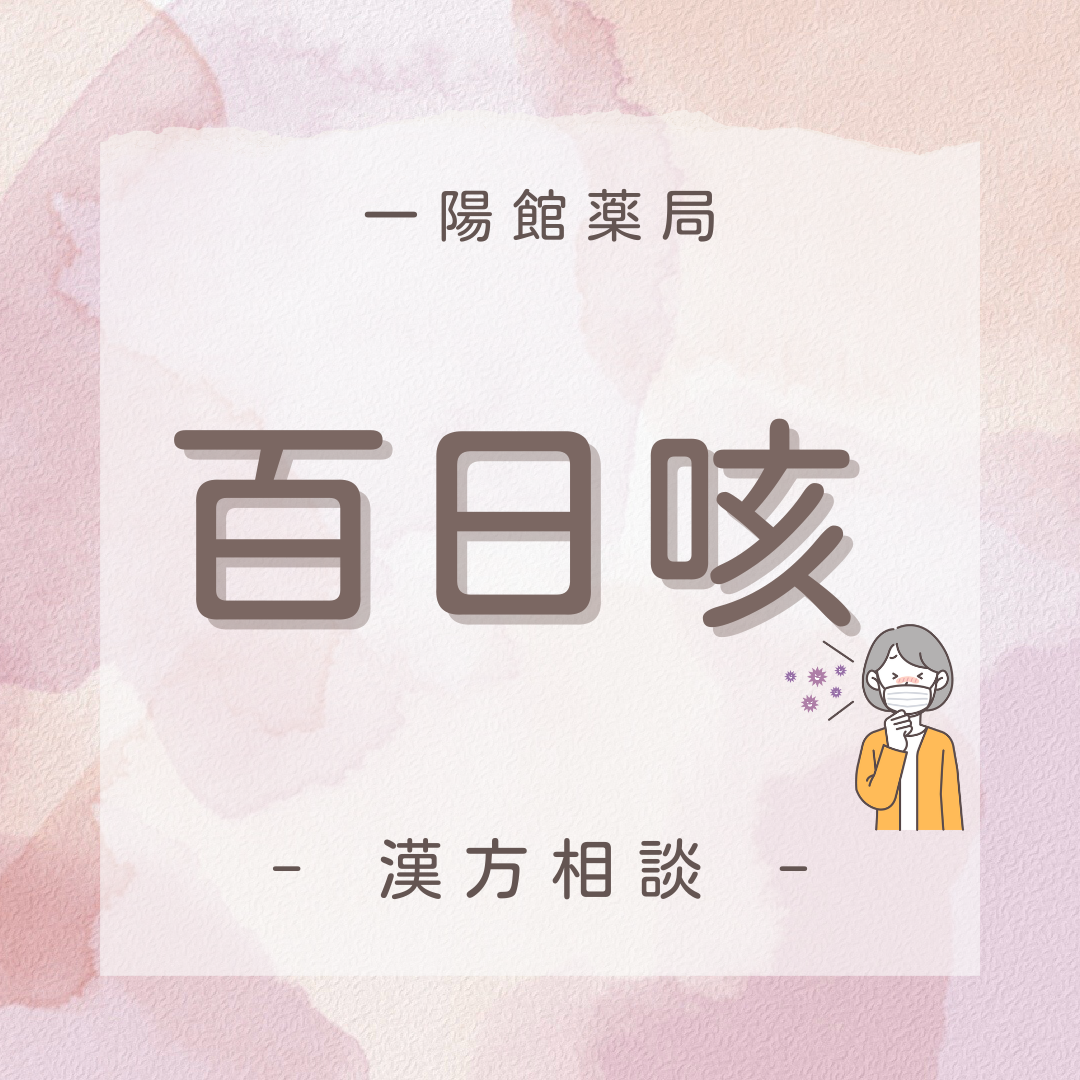【春の熱中症】油断大敵!体がまだ慣れていない春こそ注意
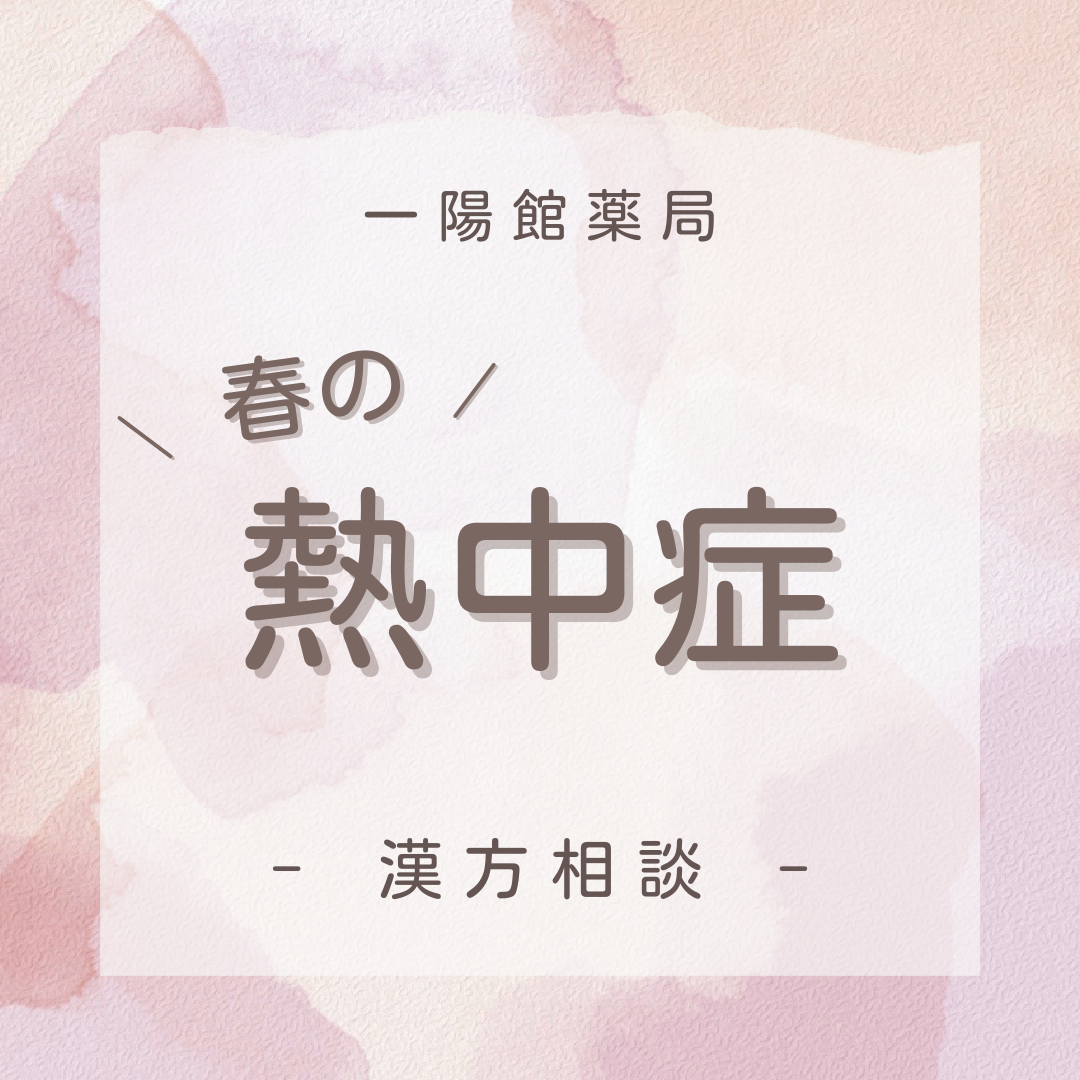
急激な暑さにより、体の疲れがとれない方が増えています。
「熱中症」と聞くと、真夏の炎天下で起こるものというイメージが強いかもしれませんが、実は春の時期から熱中症は発症しており、救急搬送される方も少なくありません。
背景には、「急激な気温の上昇に体が慣れていない」という大きな要因があります。
◆ 春の熱中症とは?
春(4月〜5月)は気候が安定せず、寒暖差が激しくなりやすい季節。
突然25℃以上の夏日になることもあり、体温調整が追いつかないまま屋外で活動すると、脱水や体温上昇により熱中症のような症状が現れることがあります。
◆ 「暑さ」だけが原因じゃない。体の中にこもる“邪”
東洋医学では、外部環境の影響を「六淫(ろくいん)」という邪気の形で表現します。春から初夏にかけては、「風邪(ふうじゃ)」「湿邪(しつじゃ)」「暑邪(しょじゃ)」といった複数の邪が重なりやすい時期です。
特に春の熱中症は、まだ「暑熱」が本格化していないうちに、急激な気温変化や湿度の上昇が加わることで、身体の内に余分な熱(内熱)がこもることで起こりやすくなります。
また、汗をかくことで体内の「気(エネルギー)」や「津液(しんえき:体の潤い)」が奪われ、体がだるくなったり、立ちくらみや頭痛、倦怠感として現れることもあります。
◆ 春は「肝」の季節。気が上がりやすく、バランスが崩れやすい
五行論では、春は「木」に属し、対応する臓腑は「肝(かん)」とされています。
肝は気血の流れをスムーズに保ち、情緒や自律神経とも深く関わる存在。
そのため、春は気温や気圧の変化とともに、気の巡りが乱れやすく、のぼせ・イライラ・不眠・めまいなどが起こりやすい時期でもあります。
急に汗をかくような陽気になると、肝のエネルギーが過剰に上昇し、「陽盛(ようせい)」という状態になりやすくなります。これが体内の熱感、のぼせ、発汗の異常といった症状に結びつき、結果的に春の熱中症を引き起こすのです。
◆ 「水」と「熱」のバランスを整えることがカギ
東洋医学では、体内の水分代謝を司るのは「肺・脾・腎」の連携です。
春の熱中症では、湿気と熱が体内にこもる「湿熱(しつねつ)」という状態がしばしば見られます。
湿が多すぎる・・だるさや胃腸の不調
熱がこもる・・・頭痛やほてり、のぼせ
水分が不足・・・喉の渇きや便秘、肌の乾燥
このように、「熱」と「水(津液)」のバランスの乱れがさまざまな不調として表れます。
春の熱中症予防には、こまめな水分補給に加え、体内の巡りを良くすること、そして余分な熱や湿をためないことがポイントになります。
◆ 春の熱中症を防ぐための漢方的な養生法
日常生活の中でも、漢方の知恵を取り入れることで、春の熱中症はぐっと防ぎやすくなります。
・冷たい飲み物は胃腸を冷やすため、常温または白湯で水分補給を行いましょう。
・積極的に香味野菜を取り入れる:しそ、ミョウガ、セロリ、春菊などがおすすめです。
・肝の働きは夜の睡眠中に整えられるため、夜ふかしは控えめにしましょう。
・軽めの運動で代謝を高めておく
春の熱中症は、「まさかこんな時期に?」という油断が一番の落とし穴。
特に「急激な気温の上昇に体が慣れていない」この季節は、無理をせず、心と体のバランスを整えることが大切です。
漢方の知恵を取り入れながら、毎日の体調変化に耳を傾けて過ごしてみてくださいね。
「なんとなく調子が悪いな」と思ったら、それが体からの大切なサインかもしれません。
営業時間 10:00~18:00
定休日 木・日・祝
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-