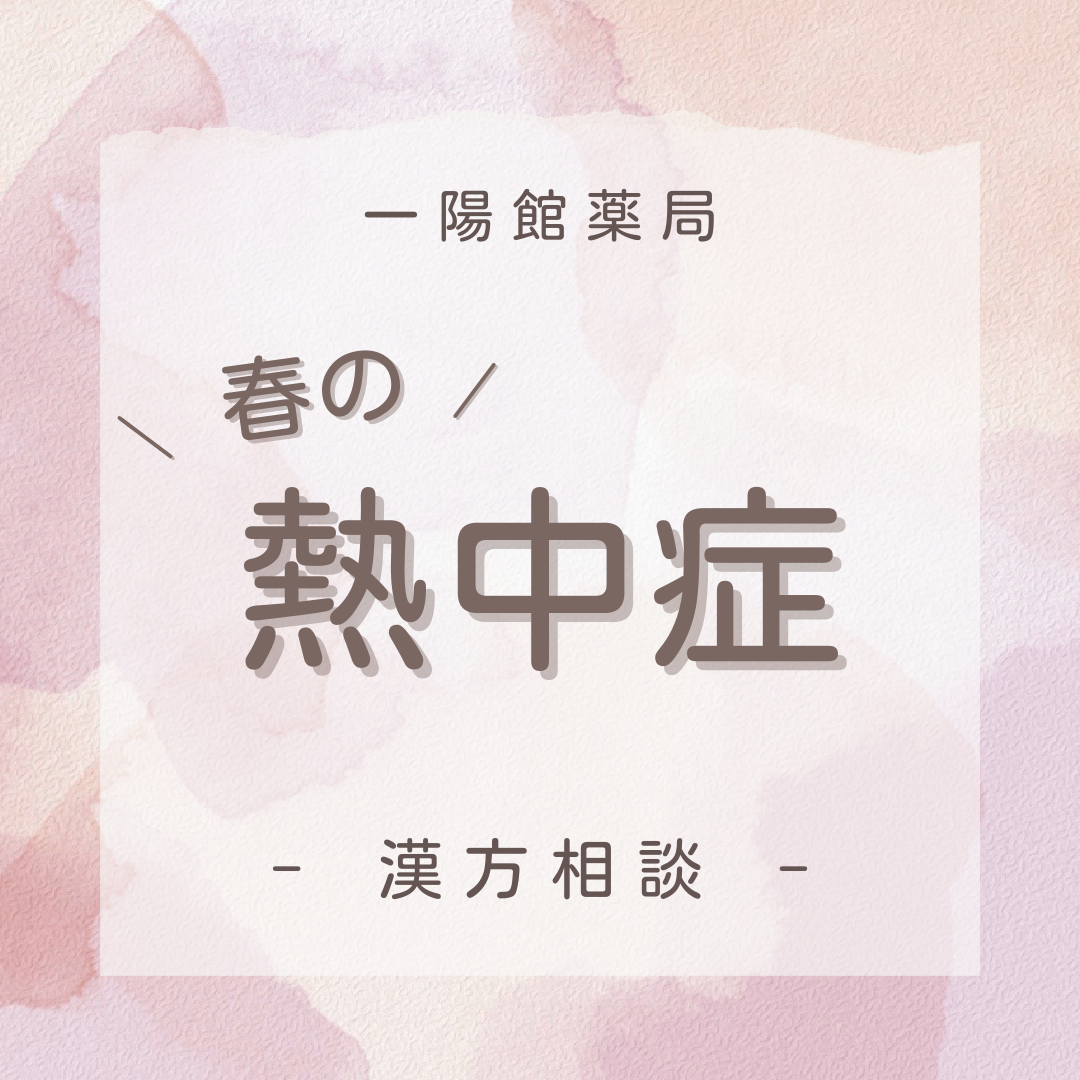女性の”なんとなく不調”、もしかして睡眠時無呼吸症候群かも?
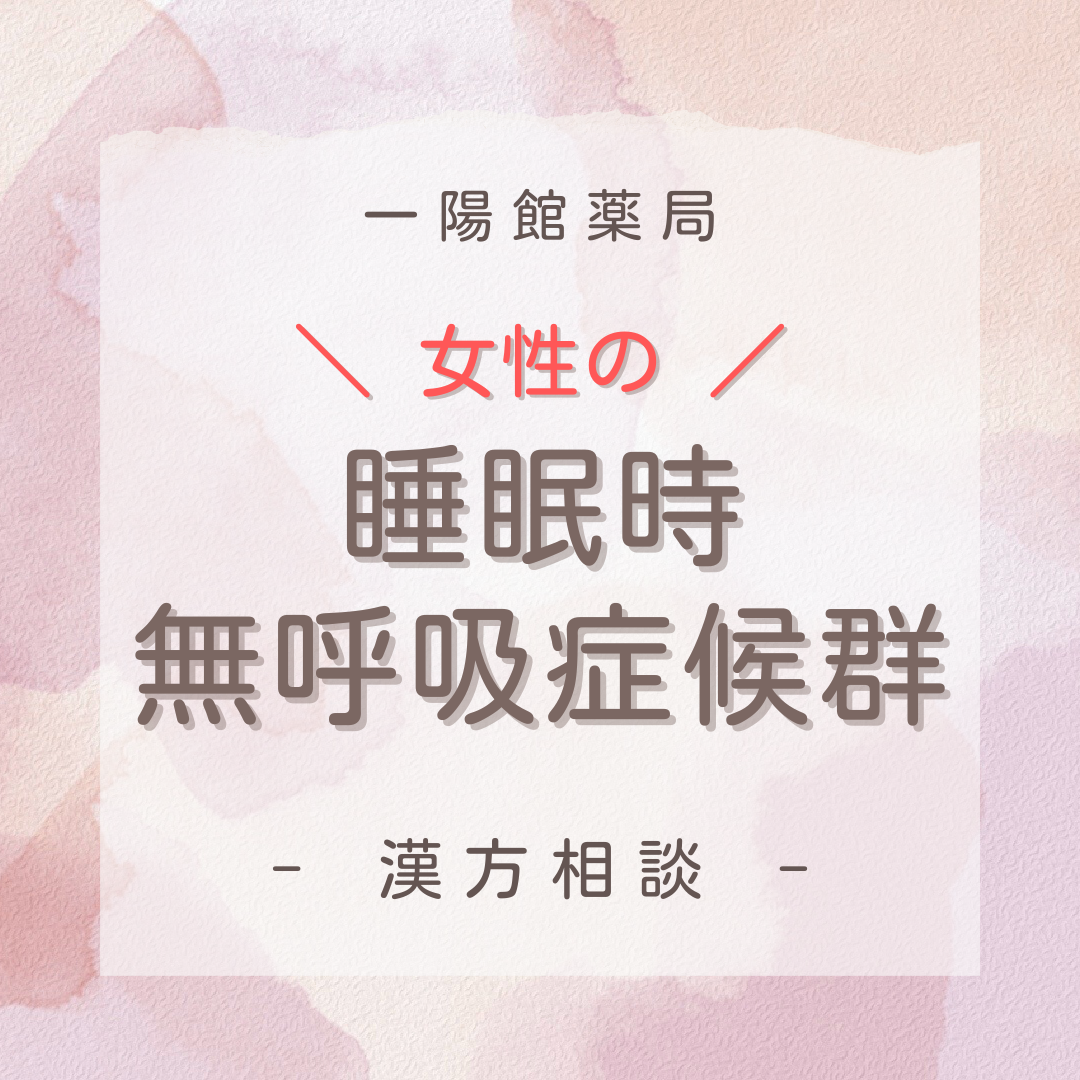
「夜はしっかりと寝ているはずなのに、朝からだるい」「なんだかスッキリしない日が続いている」といったお声を、よく耳にします。
そのお悩み、実は睡眠時無呼吸症候群(SAS)が隠れている可能性があります。
特に女性の場合、いびきや眠気といった典型的な症状が出にくく、気づかないまま放置されやすいのが特徴です。
~睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?~
SASとは、睡眠中に呼吸が止まる、または著しく浅くなる状態を繰り返す病気です。
【医学的定義】
「10秒以上の呼吸停止(無呼吸)」が、1時間あたり 5回以上 起きると診断対象。
「無呼吸・低呼吸の回数(AHI)」が10を超えると、日常生活への影響が出やすくなります。
<発症率(データに基づく)>
アメリカのWisconsin Sleep Cohort Studyによると、
SASの有病率は、
男性:24%、女性:9% とされています。
しかし、閉経後の女性ではリスクが大幅に上昇し、男性と同等に。
日本でも、40~60代女性の潜在的なSAS患者が多く、未診断のケースが非常に多いと報告されています。
◆なぜ女性に多いの?
女性は月経・妊娠・出産・更年期といったライフステージでホルモン変化が大きく、自律神経が乱れやすい体質です。
東洋医学では「腎は成長・生殖・老化を司る」とされ、SASの発症リスクが高まる閉経期は、まさに腎虚が進む時期と重なり、軽度でも生活の質を著しく下げてしまう病気です。
女性のSASは男性とは異なり、以下のような「非典型的な症状」が目立ちます。
✔ 熟睡感のなさ、夜中に何度も目が覚める
✔ 日中の慢性的な疲労感・眠気
✔ 朝の頭痛
✔ 抑うつ感・情緒不安定
✔ 冷え・むくみ・食欲の乱れ
これらの症状は、更年期障害や自律神経の乱れ、うつ症状と重なる部分も多く、見逃されやすいのです。
◆東洋医学で読み解く「女性のSAS」
東洋医学では、睡眠障害全般を「不寐(ふび)」と呼び、体全体の気(エネルギー)・血(栄養)・水(体液)のバランスの乱れが深く関係していると考えます。
特にSAS(睡眠時無呼吸症候群)の背景には、「痰濁(たんだく)」「気虚(ききょ)」「腎虚(じんきょ)」「気滞(きたい)」などの体質的な偏りが絡んでいることが多く見られます。
ここでは、代表的な4つの体質タイプと、漢方的な対策をご紹介します。
まず最も多いのが、「痰濁(たんだく)タイプ」です。
このタイプは、体の中に余分な水分や老廃物(=痰湿)がたまり、巡りが悪くなっている状態です。体が重く感じたり、頭がすっきりしなかったり、いびきや肥満傾向がある方によく見られます。漢方では、痰湿を取り除き、体内の巡りを改善していきます。
次に、「気虚(ききょ)タイプ」です。
これは体のエネルギーが不足している状態で、常に疲れていたり、声に力がなかったり、日中の眠気が抜けないという症状が出やすい傾向があります。体がエネルギー不足のために、深い眠りにつけず、睡眠の質も低下しやすいのが特徴です。気を補い、活力ある状態を取り戻すことを目指します。
三つ目は、特に閉経期以降の女性に多い「腎虚(じんきょ)タイプ」です。
東洋医学で「腎」は、成長・生殖・老化を司る重要な臓であり、加齢によって腎の力が弱まると、睡眠・呼吸・ホルモンバランスにも影響を及ぼします。腎虚の人は、冷え、頻尿、腰痛、不安感、足腰のだるさなどを感じやすく、これがSASの発症とも関係しています。
最後に、「気滞(きたい)タイプ」についてです。
これは、ストレスや感情の抑圧などによって、気(エネルギー)の流れが滞った状態です。胸の圧迫感や喉の詰まり感、不安感やイライラといった精神的な不調が強く出やすく、呼吸が浅くなったり、夜間に目が覚めたりするケースもあります。気滞タイプには、気の流れを整え、情緒を安定させる漢方が適しています。
これらの体質は、単独で現れることもあれば、複数が絡み合っていることもあります。
そのため、自分の体質を知り、根本から整えることが、質の高い睡眠と快適な毎日への第一歩になります。
◆こんな方はチェックを!
✔ 朝すっきり起きられない
✔ いつも疲れているのに、寝つきが悪い
✔ 心配ごとがあると胸が詰まる感じがする
✔ 「更年期かな…」と思っていたけれど、何をしても改善しない
そんな方は、ぜひ一度、睡眠の質や呼吸の状態を見直してみてください。
そして、ご自身の体質を知ることで、あなたに合った漢方がきっと見つかります。
一陽館薬局は、スタッフが全員女性のため、安心してご相談くださいませ。
営業時間 10:00~18:00
定休日 木・日・祝
-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
-240x240.png)